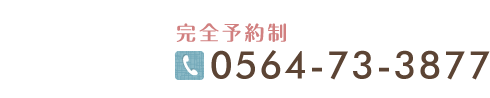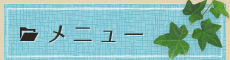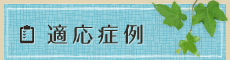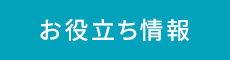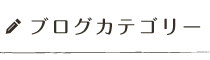「雨が近づくと頭が痛い」「季節の変わり目は体が重い」――。
そんな症状を感じたことはありませんか?
当院に来られる方の中にも、寒くなってきて症状が悪化した、天気が悪いと症状が強くなるとおっしゃる方もいらっしゃいます。
このように天気や気圧の変化に合わせて体調が悪くなる状態は、**気象病(天気痛)**と呼ばれています。
特に最近は寒暖差も大きく、気圧変化と重なることで不調を訴える方が増えています。
なぜ天気で体調が変わるの?
人間の体は、外の環境変化にあわせて体温・血流・自律神経のバランスを調整しています。
ところが、急な気圧の低下や気温差が大きい日には、体がその変化に追いつけず、さまざまなストレス反応が起こります。
特に気圧が下がると、耳の奥にある「内耳」が刺激を受け、そこから交感神経(体を緊張させる神経)が優位になり、
-
首や肩のこり
-
頭痛
-
めまい
-
倦怠感や眠気
といった症状が出やすくなります。
また寒暖差が大きい時期は、体温を逃さないために筋肉が緊張しやすく、血流が滞ることで痛みやこわばりが強まります。
研究からわかる「気象病の特徴」
ある研究では、慢性的な痛みをもつ方のうち約25%が天候によって痛みが悪化すると回答し、その7割以上が首や肩の痛みを訴えていました。
また、痛みの強さよりも「自分ではどうにもできない」「また悪くなるかも」という不安や予期的ストレスを強く感じている傾向があることも報告されています。
つまり、気象病は身体的な反応だけでなく、心理的ストレスとも深く関係しているのです。
気圧の変化を「避けられないストレス」と感じると、脳や自律神経の緊張がさらに高まり、痛みを助長してしまう悪循環に入ってしまいます。
対策のポイントは「体を整え、心を安心させること」
櫻井先生らは、気象関連性疼痛の対策として
-
痛み日記+天気の記録(気圧・気温・湿度)をつけ、自分の傾向を把握すること
-
天候の変化が予想されるときに、予防的な運動やセルフケアを行うこと
が有効だと報告しています。
自分の体調の変化と天気を記録することで、
「この気圧のときは調子が悪くなる」などパターンが見える化し、
「前もって対策をとろう」という**自己コントロール感(自己効力感)**を高めることができます。
この“自分でできる”という感覚が、不安をやわらげる重要なステップになります。
予防的なセルフケア
天気や気圧は変えられませんが、体の反応を穏やかにする工夫は誰にでもできます。
次のような習慣が特におすすめです。
1️⃣ 胸を開く深呼吸と首回し
→ 呼吸筋や首・肩の筋肉をゆるめ、自律神経を整える。
2️⃣ 耳・首まわりを温める
→ 内耳や筋膜の循環を改善し、気圧変化への反応を和らげる。
3️⃣ 軽いウォーキング・ストレッチ
→ 体温調節力を高め、寒暖差のストレスに強くなる。
また、痛みが出やすい前日や気圧が急降下する予報の日には、早めに体を温め、睡眠・水分・呼吸を意識して整えておくと良いでしょう。
まとめ
気象病は「気圧や寒暖差という外の刺激」に、「体の緊張」と「心の不安」が重なって起こります。
大切なのは、天気を変えようとするのではなく、自分の体と向き合い、整えること。
天気や季節の変化をうまく受け流せる体づくりができれば、痛みや不調は確実に軽くなっていきます。
“天気に振り回される体”から、“天気とうまく付き合える体”へ。
小さなケアを積み重ねて、気象の変化に負けない秋冬を過ごしましょう